
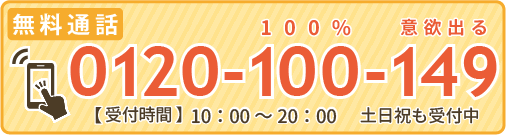
次のⅠ~Ⅳは、ある生徒が古代から近世までの農村に関する資料をまとめたカードである。あとの(1)~(4)に答えなさい。
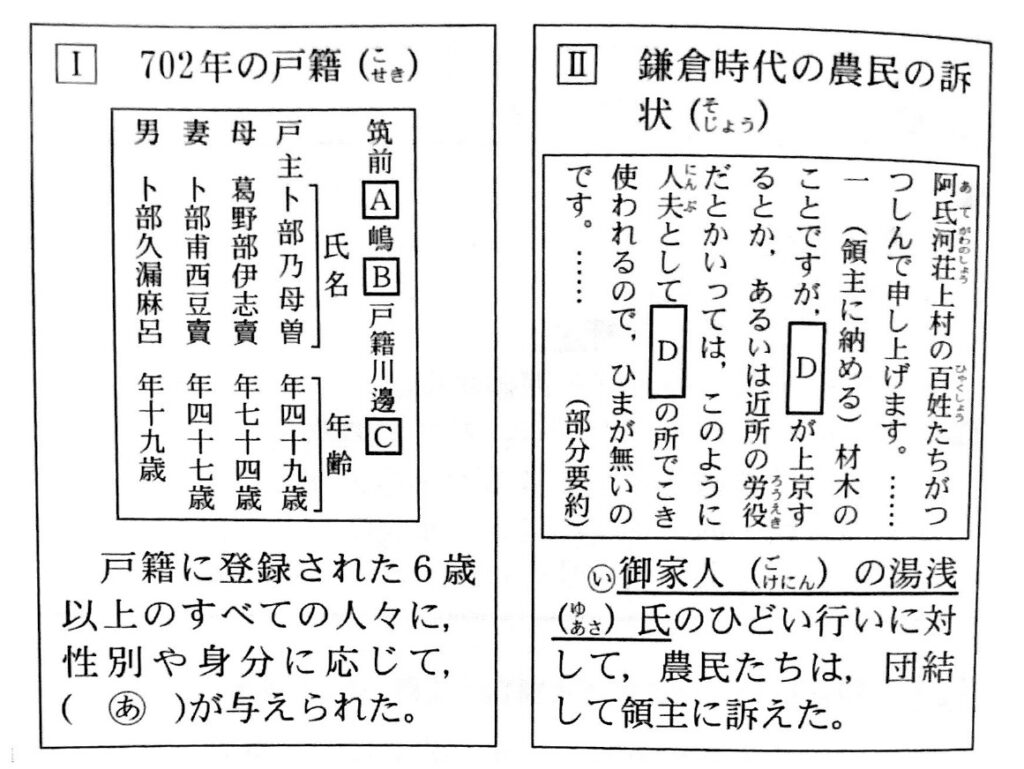

ア (あ)にあてはまる語を書きなさい。
イ A~Cにあてはまる、律令体制における地方行政の区分の正しい組み合わせを、次の1~6の中から一つ選び、その番号を書きなさい。
1 A-郡 B-国 C-里
2 A-里 B-郡 C-国
3 A-国 B-里 C-郡
4 A-国 B-郡 C-里
5 A-郡 B-里 C-国
6 A-里 B-国 C-郡
ア 下線部「う」のころに栄えた、桃山文化の特色について述べた文として適切でないものを、次の1~4の中から一つ選び、その番号を書きなさい。
1 狩野永徳は、城の室内におかれた、ふすまや屏風に、力強く豪華な絵をえがいた。
2 井原西鶴は、武士や町人の生活を基に浮世草子を書き、庶民の共感を呼んだ。
3 千利休は、禅宗の影響を受け、内面の精神性を重視し、質素なわび茶の作法を完成させた。
4 出江の阿国という女性が始めたかぶき踊りが人気を集めた。
イ (え)に共通してあてはまる語を書きなさい。
ア 口分田
イ 4
国・郡・里の順番で小さくなる。
守護は国ごとに置かれ、軍事や警察に関する役目を担い、地頭は荘園ごとに置かれ、税の取り立てが主な仕事だった。
ア 2
井原西鶴は江戸時代の人
イ 石高
短期間で効果を出すなら
家庭教師のひのきあすなろ!